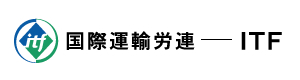| No.23/2009 |
| ■経済危機 |
 |
| |
船員も異常事態を実感
世界経済危機は、急速かつ凶暴な力で世界を襲い、海運業界も大きな打撃を被った。ブレンダ・カーシュが現状と船員への影響を分析する。
背景
2007年、金融会社が低所得者層の資産購入を促進するために、ハイリスク戦略を採用していることへの懸念が米国で浮かび上がってきた。当初は、小規模で地域的な問題と見られていた。
米国の金融業者らの投機的投資の行き過ぎとして始まったこの事態は、世界の経済と数百万人の生活と職場に影響を及ぼすこととなった。信用危機の影響は急速に拡大し、かなりの期間継続すると思われる。海運業界と船員も、大きな打撃を受けている。
信用の縮小にともない、中国、インド、東南アジア諸国の工場の受注も減少した。その結果、アジアから北米やヨーロッパへのコンテナ輸送需要は急落した。海運会社も拡大と成長路線を見直し、新造船の発注を減らしている。
売上収入の減少と銀行の貸し渋りは、クルーズ船観光やその他の船旅レジャーの需要にも悪影響を及ぼしている。
このような現状が、就航船舶数に直接の影響を及ぼし、造船産業や将来の景気回復に対応するための海運産業の能力に、長期的な影響を与えている。
海運業界は、昨年は燃油価格の高騰、石油生産量と供給量の削減に苦しめられた。また、アデン湾の海賊の脅威のために、一部の船社はアジアからヨーロッパへの航路を、より日数と経費のかかる航路へと変更している。そのため、輸入品のコストがさらに高まっている。
|
|
 |
海運と経済危機
国際経済の衰退は、2008年度には、海運業界に打撃を与え始めた。撒積船の用船料の急速・大幅な下落は、海運大手の用船主および船主を直撃した。経済環境の悪化は、貨物運賃の急降下となって表れた。
2008年6月までに、コンテナ船の輸送量は落ち込みを示していた。第2四半期の数字を見れば、西回り貨物の増加率は5.24%で、第1四半期の11.62%から減少し、1年前との比較では20%の減少となっていた。
北部ヨーロッパ向けのコンテナ貨物の伸びは、第1四半期の9.3%に比較して、僅か3.6%に減少した。2008年6月の西回り貨物の全仕向け地向け貨物の総量は1%拡大したが、2008年5月の増加量は9.35%であった。
9月のリーマン・ブラザース投資銀行の破綻と、企業への金融収縮の強化などによる米国株式市場の値下がりによって、混乱はさらに増した。米国政府は、経済危機の打撃によって、破綻に瀕していた保険会社AIGに融資をせざるを得なかった。AIGは海上保険の大手であり、米国最大の港湾経営企業であるポート・アメリカ社の所有者でもあった。
例年ならばアジアからヨーロッパ向けの海上貨物は、クリスマスを控えて活況を呈するはずだが、2008年は何事もなく終わった。
モーガン・スタンレー投資銀行アジア地区頭取のスティーブ・ローチは、2008年11月に中国で開かれた世界海運サミットにおいて、世界経済の減速は少なくともあと2年間は続く可能性があると警告した。
|
|
 |
船員への影響
海運貨物輸送量の減少が船員の職場に影響を与える以前から、船員は賃金への影響を実感していた。多くの船員は賃金をドルで受け取っているが、2008年中頃からドルの価値が下がり始めたのである。船員とその家族はドル安の影響を直ちに被ったが、船員を含む海外派遣労働者の送金に依存しているフィリピンなどの国家経済も打撃を受けた。(下の記事参照)
2008年7月にシップトーク・リクルート社が行った船員(職員主体)調査によれば、多くの船員がドル安によって損害を被っており、70%以上が、賃金が家計費の上昇に追いついていないと回答している。
また、乗組員の賃金の凍結、場合によっては引き下げを船社が求めるのではないかとの懸念が増大している。ITF加盟の英国船舶職員労組(ノーチラス)は、すでに一部のコンテナ輸送企業およびクルーズ船企業から賃金凍結の提案を受け、交渉を行っている。
船舶が海外就航中に海運会社の経営が破綻した場合、乗組員は賃金未払いのまま、食糧もないままに海外の港に、船とともに遺棄される恐れが、現実の問題となってきている。ITFは現在、海運企業が倒産し、船舶が遺棄された場合の乗組員援助や異常事態への対応のガイドラインをインスペクターのために策定中である。
しかし、問題は賃金カットだけではない。経済危機は今や、職場の数の縮小や船員の失業増大といった問題を引き起こしている。
「景気後退の影響が船員に及んでいるという明らかな証拠を我々は得ている。いくつかの船社がすでに倒産し、世界各地の港で、船員が賃金未払いのまま遺棄されている」とITFのファブリツィオ・バルセロナ海事活動部長は語る。彼はITFインスペクターの活動ならびに困難に直面する船員のための日常的援助の責任者であり、経済不況の影響を身近に感じている。
「中国やインドの原材料輸入の減少は、撒積船の余剰となって表れている。バラ積み船、コンテナ船それに一般貨物船などの市場に参入している大半の海運会社は、就航船舶隻数の削減、採算割れ航路の休止などの再編を行っている。船舶は港に係留され、乗組員は次の職場のあてもないまま、本国に送還されている。ITFは市場の動きに常に注意を払っており、既に何人かの船員に対して、未払い賃金や本国送還費用の獲得を支援してきた。長期的観点から見れば、船舶職員を解雇すれば、将来景気が回復したときに、適当な資格と技能を有する船舶職員・部員が不足する事態に陥る。ITFは景気が回復したときのためにも、船舶職員の訓練の必要性を繰り返して主張している」とバルセロナ部長は述べた。 |
|
 |
| ●ブレンダ・カーシュは、ロンドンを拠点として活動するフリーのジャーナリスト。 |
 |
フィリピンへの影響
世界の船員の多数を占めるのはフィリピン人船員で、約30万人以上になると見られている。また、フィリピン国民が稼ぐ外貨は、フィリピンの重要な国庫収入の一部となっている。海運を含むいくつかの産業に就労するフィリピン人労働者が海外から送金する外貨は、2008年1月〜10月までで137億ドルに達し、フィリピン国家経済の12%以上がこれに依存しているとされている。この外貨収入の価値が、ドル安と国内のインフレの進行で打撃を受けている。
海外就労するフィリピン人労働者の中には、倒産、人員整理、リストラ、仕事の減少などの影響を受けて、既に解雇されている者もいる。フィリピン政府は、世界経済危機の影響で解雇された海外就労のために、このほど「払い戻し制度」を発足させた。
|
|
 |
莫大な損害その被害者
●ウクライナのバラ積み船・タンカー運航企業であるインダストリアル・キャリヤー社は、2008年10月、破産申請した。この企業は52隻を用船・運航していた。
●台湾のコンテナ輸送会社のヤンミン海運公司は、2008年に2隻、2009年央には、さらに8隻のコンテナ船の運航を停止した。
●シンガポール政府が所有するネプチューン・オリエント・ライン(NOL)とパートナーの商船三井(MOL)および現代商船(HMM)は、計40隻の船舶の運航を休止した。さらに、NOLは一部の航路のコンテナ船の船腹量を約25%削減している。
●シンガポールのパシフィック・国際ラインおよび台湾のワンハイ・ラインは、2008年12月、両社によるアジア/欧州航路の共同運航を中止した。
●長距離コンテナのCKYH連盟[Cosco(中国)、KLine(日本)、ヤンミン(台湾)、韓進(韓国)が参加]は、2008年11月、アジア/北ヨーロッパの週あたり輸送量を9%縮小した。さらに、韓進海運は、北米−欧州航路の就航隻数を削減した。
●デンマークのマースク・ライン(世界最大のコンテナ輸送会社)は、アジア−欧州航路、アジア−中米航路、太平洋横断航路などの就航隻数をカットし、コンテナ船8隻の係船を発表した。同社のアジア−ヨーロッパ航路の貨物取扱量は、2008年第2四半期の2%減に続いて、2008年第3四半期は前年比3%減となった。貨物取扱量の前年比減は、この航路の40年の歴史上、初めてのことだ。
●CMA CGMおよびチャイナ・シッピング社は、共同運航の隻数をカットすることとなった。
●世界第2のコンテナ輸送企業である地中海海運(MSC)は、アジア−欧州航路の輸送能力を5%削減したほか、アジア−黒海航路の運航を中止した。
●韓国のC&L海運は、2008年10月に運航を停止した。これまで同社は、24隻の船舶を用船し、アジア地域の20以上の航路で運航していた。
●日本最大の営業実績をあげている日本郵船(NYK)は、自社の船腹拡大計画を約25%(50〜60隻)縮小することにした。
●台湾のエバーグリーン海運グループは、2008年第3四半期の純益が94%落ち込んだと発表した。
●韓国の造船所(複数)は、多額の赤字を計上している。この状況は今後も続くと見られている。
●日本の辻産業は、破産手続きを開始した。同社は、船舶の46隻の受注残を抱えている。
●英国のフェリー大手企業のP&Oフェリー社とレッド・ファンネル社は、便数の削減と採用の凍結を発表した。 |
|
 |
| |