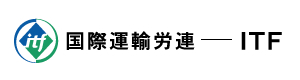|
 |
| No.23/2009 |
| ■共に立ち上がろう |
 |
| |
共に立ち上がろう
ブレンダ・カーシュが、船員と港湾労働者の労働組合運動の歴史的関係を概観する。
港湾労働者の呼び方は、国によって異なる。同じ英語を使う国によっても異なる。しかし、貨物の荷役は熟練を要する仕事であり、船員が自らの手で荷役を行うよう圧力を受けても、船員は港湾労働者の仕事を伝統的に尊重してきた。船員はその技能を駆使して、船舶を港湾まで運航し、港湾労働者はその技能を駆使して、船舶が輸送してきた貨物の陸揚げまたは積み込みを行う。このことについて、船員労組と港湾労組は合意しており、ITF団体協約でも、船舶乗組員は貨物の荷役を行うべきではない、と規定されている。
港湾労働者の権利を保護し、改善するための組合運動には、しばしば激しい闘争を含む長い歴史がある。初期の例として、1886年のロンドン港湾ストライキがある。搾取に苦しむ当時の港湾労働者が、1時間につき6ペンスの「日焼け手当」を要求したのだ。ストは成功を収めただけでなく、この時の運動が、日雇い労働者を労働組合に加入させる基礎となり、その後さらに、英国最大最強の労組と言われた運輸一般労組(TGWU)へと発展したのである。
港湾労働者と船員の連帯の最も初期の例は、1896年のロッテルダム港湾ストライキである。アントワープの港湾労働者だったITFのフランク・レイ港湾部長は、今も昔も問題は変わっていないと指摘する。それは「新」技術の導入である。19世紀末の新技術の導入とは、貨物荷役におけるクレーンの登場だ。ロッテルダムのストに際して、港湾労働者は欧州の仲間に支援を求め、英国船の乗組員が荷役に従事することを拒否した。この時の連帯行動によって、ITFの前身である船員・港湾・河川労働者国際連盟(IFSDRW)が結成されたのだ。
「貨物の荷役は、この頃から一段と熟練を要する職業となってきた。今日の港湾荷役には、一連の先端技術が導入されている」とレイは言う。厳しい肉体労働分野の大部分に技術が導入された結果、港湾労働者の数は減少した。「アントワープ港の労働力は、20年前に比べて半減し、現在は7千人になっている」
科学技術は船内業務も変化させている。「船舶は大型化する一方、乗組員の削減が一段と進んでいる」とレイは指摘する。最新科学技術の利益は、関連する労働者の利益となるべきで、彼らの搾取に利用されるべきではない。
「船員は荷役を強いられるべきではない」とレイは言う。「入港時には乗組員は疲労している。その上、港湾滞在時間の短縮のために、乗組員は十分な休息時間が取れなくなっている。ゆえに、船員が港湾労働者の仕事を命じられるべきではない。港湾荷役は、適切な訓練と適正な安全用具を備えた港湾労働者によって行われるべきだ」 |
|
 |
条約とキャンペーン
港湾作業と貨物荷役については、二つの国際条約が国際労働機関(ILO)で採択されている。職業における健康と安全(港湾労働)条約第152号および港湾労働条約第137号である。第152号は26カ国、第137号は24カ国にしか批准されていない。しかし、批准国数が少ないからといって、各国政府が港湾労働条件の保護を支持していないというわけではない。安全衛生に関する事項は、国の管轄ではなく、地域または地方政府の管轄となっていることが多いのだ。実際、第152号条約および第137号条約の規定の多くが、国の法律や企業の方針に導入されている、とレイは指摘する。
一方、労働者の権利に関して、抜け道を探そうとする動きが少なくないことも、また事実である。2006年には、船舶乗組員の荷役を認めるEU指令を導入させようとする動きがあったが、「EU諸国の港湾労組による強力な圧力」によって、導入は見送られた、とレイは語る。「港湾労働者が団結し、港湾労働者であることに誇りを持っていることを示した結果、この試みは敗退したのだ」
世界各地の港湾で働く港湾労働者のための受け入れ可能な基準を設けるために、ITF港湾部会は「便宜港湾(POC)」反対キャンペーンを実施している。民営化とグローバル化の拡大は、世界の港湾貨物取扱量の58%を大手4社が占めるという事態をもたらしている。大手4社とは、ドバイ・ポート・ワールド、PSAインターナショナル、APモラー・マースク、ハッチソン・ポート・ホールディングスである。
POCキャンペーンの目的は、日雇い化、民営化、新技術に直面している港湾労働者の労働条件を守ることだ。安全衛生は、労使が協力して取り組むことができる、あるいは、取り組むべき問題だ。
レイは言う。「港湾労働者がいなくなったら、船員が困難に陥ったときに、誰が手を差し伸べるのだろうか?」 |
|
 |
| ●ブレンダ・カーシュは、ロンドンをベースに活動するフリー・ジャーナリスト。 |
 |
港湾での連帯
港湾労働者と船員は、ITFのFOCキャンペーン活動に共に参加している。
昨年10月のバルト海地域行動週間中にドイツの船員と港湾労働者がデモ行進を行った結果、スウェーデン籍のステナキャリアー号の船主は、伝統的に港湾労働者が行っている作業を船員に指示しないことに同意した。
「この船は、スウェーデンとドイツの間を定期的に運航している」とITFのドンリー・ハーは説明する。「これまで、貨物のラッシングは港湾労働者と船員が共同で行っていた。ところが、ステナ社は港湾労働者抜きでラッシングを行うよう、自社の船員に指示し出した。港湾労組の要請によって、ITF行動週間のドイツチームは、ステナ社に対する抗議集会を1時間行った」
「交渉の結果、会社側は今後、伝統的な港湾作業を船員に指示することはしないとの合意が成立した。これは港湾労働者と船員の双方にとっての勝利だ」
この行動週間には10カ国の船員、港湾労働者および組合関係者が参加した、とドンリーは言う。「船員と港湾労働者が相互に学ぶだけでなく、共に行動することによって、船員と港湾労働者の緊密な関係が立証された。労働者が団結すれば、決して負けることはない、というメッセージを船主側に明確に示すことができた」
11月の東南アジア行動週間においては、インドネシアの港湾労働者が、日本所有船の荷役業務を遅延させた。ITFインスペクターが、この船舶に全日本海員組合(JSU)の協約が適用されていないことを発見したからだ。その後、ITF、関係労組、船主および用船者の間で4時間にわたる交渉が行われ、協約が調印された。
韓国では、船員労組の抗議集会に港湾労組が参加した。日本の神戸港および大阪港では、港湾労働者がターゲット企業の興徳海運の所有船舶の荷役を中止した。 |
|
 |
| |
|
 |
|