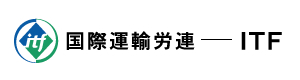|
 |
| 2004年1月 第14号 |
| ■勤労生活 |
 |
| |
勤労生活
グローバル化と私たち
2004年1月にボンベイで世界社会フォーラム(WSF)が開催される。そこで、ボンベイの交通運輸労働者にグローバル化の影響について聞いてみた。
アビシェク・バルガバ(32歳)
西部鉄道マハラキシミ店舗部
インド鉄道の経営が悪化する中で、現場の環境も厳しくなっている。新規採用は停止され、業務量も増えている。もちろん組合も対策を行っている。そうでなければ、インド鉄道はとっくに民営化されていただろう。組合に足りないのは、WTO、多国籍企業、市場経済、グローバル化などに関する教育活動だ。教育活動は組合の動員力を増し、われわれの抵抗運動に意味をもたせてくれる。
プラシャント・ナラヤン(34歳)
エア・インディア、サービスエンジニア
技術進歩と労働基準の向上はグローバル化の成果ではあるが、グローバル化は同時に、人員削減と雇用機会の喪失というマイナスの影響ももたらした。私の部署の人員数は94年から増えていないが、高い生産性を維持してきた。エア・インディアが生き残るために、職員全員が100%以上の力を出しきっているからだ。
組合は正しい方向に向いている。エア・インディアを民営化する必要はない。何か別のアイディアが求められている。利益を出すために職員を解雇すればいいというものではない。
ヴィカス・R・グプテ(41歳)
西部鉄道マハラキシミ印刷所 校正担当
先進国が自国の財・サービスを売る市場を世界のあちこちで開拓していくこと、これが私の知っているグローバル化だ。
世界銀行は(鉄道の)印刷業務を非中核業務とみなしている。ある晴れた日の朝、印刷業務の外注化が決定された。われわれは外注化に抵抗し、闘った。その結果、九つある印刷所全てが当面、維持されることとなった。今日、残業代も奨励手当も出なくなったが、われわれは自分たちの仕事を守るためにがんばっている。労働組合はやるべきことをやっていない。組織労働者は全労働者の8%に過ぎない。小さな成果は出ているが、全体像は決して明るくない。
モハマド・シャリフ(35歳)
ムンバイ・ポート・トラスト、シニアワーカー
1995〜96年の貨物取扱量は1シフト150トンだったが、今は400トンにまで上がっている。にもかかわらずわれわれの賃金は減っている。労働者は一般的に現状認識ができておらず、教育も受けていない。組合が何でもやってくれると思っている。
組合が何をしているのか、組合が提案していることは何か、今後の方向性はどうあるべきかに関する教育や情報提供が不足している。
ニレシュ・ナルベカール(25歳)
マハラシュトラ州路面運輸公社(SRTC)、車掌
われわれの金は出ていき、製品は腐っていく。機械が人に取って代わり、失業率は増えるばかり。
業務量も増えている。1日12時間働いているが、残業代は1〜2時間分しかもらえない。病気で休んだ時でさえ、給料は引かれる。
組合はがんばっているが、団結力に欠けているため、多くの闘争で負けてしまう。
スレシュ・ソランキ(28歳)
ドッケンデール海運会社、ボースン(甲板長)
会社はできるだけコストのかからない道を追求している。たとえそれがサービスの質を悪化させようともである。かつて、船の修理はドックで行われていたが、今は乗組員がほとんどの修理業務をやらされている。修理の仕方をよく分かっていない人を安い値段で直接、雇うこともある。とにかく修理して一等航海士に報告しなければならないからだ。
組合はグローバル化のマイナス面に対抗するためにがんばっている。しかし、若い船員たちは組合があまり好きではない。困ったときだけ助けを求めるにすぎない。
ギリシュ・ムンガイン(35歳)
インド航空、監督者
われわれの仕事のほとんど(システム、機材清掃、予約、ケータリングなど)は外注化された。われわれの仕事は常に民間の航空会社との競争にさらされている。
組合はどうしてよいか分からないでいる。現在の指導部のほとんどは、保護された環境の中で育ってきた。しかし現在、ほとんどの市場が開放され、指導部は状況を一般組合員に説明できないでいる。ただ単に変化に反対するだけでなく、変化を理解し、現実に立ち向かう準備をすることが大切だ。
マヘシュ・B・ジャドハブ(30歳)
マハラシュトラ州路面運輸会社 ムンバイ中央部航空管制官
人員削減や転勤が次々に行われている。女性職員も150キロも離れた勤務地に異動命令が出されている。命令に従うか辞めるしかない。
労使関係法や労働法の改正で組合の力は弱まっている。 |
|
 |
| インタビューはサンガム・トリバシー |
 |
| |
|
 |
|