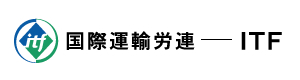|
 |
| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■組合アライアンス、ただいま参上 |
 |
| |
組合アライアンス、ただいま参上
グローバルな組織化に挑戦するための全く新しいアプローチの一環として、航空労組は活動方針を変化させているとヤスミン・プラビュダスは報告する。
2007年には2つのITF航空アライアンス会議が行われ、革新的な組織化手法が徹底的に検討された。例年通り、同じ航空アライアンスに属する航空会社で働く労働者を組織する組合の代表者が情報交換のために一堂に会したが、今年の会議は使用者と闘う仲間の組合に連帯を表明するための「真の活動の場」となり、会議自体に「付加価値」が生まれた。
「ITFのグローバルな組織化キャンペーンの影響で、今年はアライアンス会議の開催方法を試験的に変えてみた。これまでのアライアンス会議を超えるものにしたかったからだ。一つには、組合の意思決定者だけを会議に呼ぶのではなく、一般組合員も招きたかった。組合員の士気を高めるためだ」とITFのインゴ・マロスキー民間航空部長は言う。
昨年10月のスカイチーム・アライアンス会議の際に、新たな試みがまず試されることになった。スカイチームとは別の航空アライアンスに属する2組合、米客室乗務員組合(AFA)と米国際機械工・航空労働者組合(IAMAW)に連帯を表明するため、わざわざ米国のアトランタで会議を開催した。これら米国の2組合は、ちょうどその時、アトランタで集会を行い、デルタ航空の労働者を組織しようとしていた。米国以外の殆どすべての国をカバーしているアライアンスの2組合は、アトランタの集会に参加することで、デルタ航空の労働者に対する支援を表明した。
AFAのベーダ・シュック副委員長は、「この連帯行動により、世界中の客室乗務員の『共通項』が浮き彫りになった。ITFの加盟組合が集会に参加したことは、大いに役立った。スカイチーム系の航空会社は組織率が特に高いが、デルタ航空は明らかに例外だった」と述べた。
AFAのアラスカ組織化担当のジョン・コーネリウスも、こう付け加えた。「この集会に世界中の労働者が参加していることを反組合主義者に実感させることができたのがよかった。この問題にグローバルな側面を加えることができた。ややもすれば、組合は国内の問題に集中しがちだが、当該の問題の影響を受けるのは自分たちだけではないことを実感することができたのでよかった」
IAMAWの運輸担当役員で、ITF民間航空委員会の議長を務めるカーラ・ウィンクラーは、国際連帯と、組合が職場の声を代表している事実を、デルタ航空の労働者に感じてもらうことが重要だと考えた。
「国際連帯や国境を越えた連帯が、世界中の労働者の団結を図る上でいかに重要であるかが示されたし、労働者を他国の労働者と闘わせることはできないというメッセージを会社に対しても伝えることができた。我々は皆、職場で意見を取り上げてもらいたいと願っており、働きがいのある人間らしい賃金と年金をもらいたいと考えている」とウィンクラーは述べている。 |
|
 |
より緊密な協力
「ITFのアライアンス会議は同じ航空アライアンスに属するITF加盟組合同士の連携を図ることを目的に立ち上がったが、同時に、悪辣な航空会社が出現した場合に、同じ地域の加盟組合に会社に対する警戒を促したり、国際支援や連帯を寄せたりすることも目指している」
同様の国際連帯はアルゼンチンでも見られた。ワンワールド系航空会社の組合がブエノスアイレスに出向き、アルゼンチンのLAN航空で働くアルゼンチン航空連合、アルゼンチン航空従業員労組、航空ナビゲーション従業員労組の組合員を支援したのだ。これら3労組は、会社が組合の団体交渉権や、独立した組合に加入する権利などの労働基本権を軽視し続けている事に対し、懸念を募らせていた。
ITFのリズ・ウィリアムソン民間航空部次長はこう述べている。「ITFが2007年のワンワールド労組連携会議を開催したのは、LAN航空で働く仲間に対する支援を表明するためだった。会議にはワンワールドグループの労組が参加しただけでなく、アルゼンチンに加え、チリやペルーのLAN航空グループの労働者からも大きな支援を受けた。同じLANグループを組織する組合同士が初めて顔を合わせ、非常に前向きかつ協力的な議論が行われた」
上述の2つのアライアンス会議は、マスコミにも大きく取り上げられた。マロスキー部長は、「今年、ITFが目指したのは、これまで以上に先手を打った形で一般市民の共感を得ることだった。ITFのウェブサイトにも情報を載せ、ITF広報部は出版物を準備し、加盟組合にも参加してもらった。そうすることで、どちらの会議も「労組だけの会議」にはならずに済み、参加した加盟組合の活動を進展させることにつながった」と述べた。
すると今後の戦略はどうなるのか?マロスキー部長はこう補足する。「これまでは合同でアライアンス会議を開催していたが、今年はアライアンスごとに別々に会議を開いた。今後、再び合同でアライアンス会議を開催する可能性もあるだろう。状況に応じて会議の開催方法も変えていく必要があろう。2007年には、別個にアライアンス会議を開くことが絶対的に重要だったが、この取り組みは大成功だった。スターアライアンス労組の会議はまだ開催が決まっていないが、同様のアプローチを取ることになろう。あるいは、労使紛争が発生している場所で、3つのアライアンスに属する航空労組を全て結集して会議を開催することもできよう。 |
|
 |
組織化を推進
また、中東地域の航空会社のアライアンスであるアラベスク・アライアンス系航空会社の労組と協力しようという計画もある。アラベスク・アライアンスで最も大きな問題は組織化をどう進めていくかだ。中東地域を占有するエミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空や、同地域で増え続ける格安航空会社の労働者は未組織だ。アラベスク・アライアンス労組会議を開催することで、中東の航空会社の組織化を推進していくきっかけになるかもしれない。
ITFアラブ事務所のビラール・マラカウィー部長はこう述べる。「活動計画を立て、アラベスク・アライアンス系の組合と協力を進めていくことは可能だろう。現段階では、同アライアンスは主に燃油やサービス関連の問題の協議や、燃油、ケータリング、グランドハンドリングのコストをどう削減するかについての協力に止まり、労働問題を話し合うには至っていない」
ITF航空アライアンス会議の新方針を長期的にどう方向づけていくかは、加盟組合次第だ。「どこで労使紛争が発生しているのか、どこで支援が必要とされているのか、どのような形で会議を行うことを望んでいるのか、加盟組合の方からITFに連絡してくれる必要がある」と、マロスキー部長は述べた。 |
|
 |
| |
|
 |
|