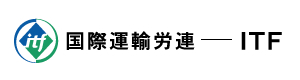|
 |
| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■論説 |
 |
| |
中国に目を向ける労働組合運動
今年は、北京オリンピック開催年だ。グローバル・ユニオンは昨年6月、「プレイフェア2008」運動を展開し、法定賃金の半分以下で労働者を働かせていることや、児童労働の使用、劣悪な安全衛生基準に関して、帽子、バッグ、文具などのオリンピック記念グッズを製造する中国の4工場を非難した。
中国のオリンピック会場では、貧しい地方出身の労働者が最低賃金以下で働かされているほか、労働者の死亡事故が隠蔽されているとの報告もある。
一方で、自らの権利を求めて立ち上がる労働者も増えている。
6カ月前、甘粛省の慶陽市運輸公司の事務所前で長期間にわたり抗議行動を展開していた労働者が、警備隊に解散させられる出来事があった。
彼らは、運輸公司が民営化され、不動産開発業者に売却された後、社会保障手当も失業手当も支給されずに解雇され、1月から事務所前で抗議行動を続けていた。
この争議を含めて、2007年8月には4件の労働争議が記録されている。労働争議を控えめに扱う政府統計でさえ、その増加率を「年27.3%」としている。
中国の労働争議の多くは、かつての国有企業の民営化に抵抗する労働者によるものだが、中には外国所有や中国所有の劣悪な工場や、建設ラッシュで需要が高まっている日雇い労働者に関係するものもある。
一方、中国は途上国のインフラに盛んに融資している。中国輸出入銀行は、天然資源豊富なアンゴラの道路・鉄道建設に20億ドル相当の融資を提供しているほか、モザンビークの現在の道路建設事業の3分の1以上に、中国の土建業者が関与している。スーダンの石油探査や鉄道輸送にも、巨額の中国資本が投入されている。
これらの投資は、中国の工業化を促進するために、資源の採掘を可能にすることが狙いだ。人権や労働組合権への配慮がなされることは、ほとんどない。中国政府は、これらを国内問題と主張している。実際、中国の「付帯条件なし」の政策は、南々協力のよい例として、多くの途上国から肯定的に受け止められている。
ITFは、中華全国総工会(ACFTU)の海事関係労組と既に接触しており、他の交通運輸労組とも真の対話を行う用意がある。ダーバン大会では、これを支援する決議が採択された。中国は、急速に変化している。何百万人もの交通運輸労働者が、今日、民営化やリストラ、搾取に直面している。
オリンピック問題は、グローバル・ユニオンにとって、2008年の多くの試練の中のほんの一つに過ぎない。闘っている中国の労働者と、どのような関係を築けばよいのか?グローバルに拡大し続ける中国資本に、どう取り組んでいけばよいのか?これらの問題は、4月のITF執行委員会の議題となるだけでなく、今年の労働組合の議論を特徴づけることになる。 |
|
 |
| |
|
 |
|