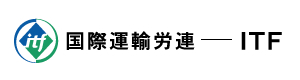|
 |
| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■地球温暖化 |
 |
| |
地球温暖化と労働組合
温暖化問題をめぐる労働組合の課題について、ルシアン・ロイヤーが語る。
ここ10年間で地球温暖化が急速に進行していることは、世界中の労働者や労働組合も認識しているだろう。温暖化の影響を直接感じることはないとしても、温暖化をめぐる出来事が毎日、新聞の見出しを飾っていることには気付いているはずだ。
国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が、気温上昇を2度以下に抑制するために、全世界の温室効果ガス排出量を2050年までに1990年比で80%削減する必要がある、と勧告しているのも頷ける。
地球温暖化をめぐっては、温暖化ガスの排出削減目標を初めて設けた京都議定書(2004年採択)が有名だが、今や世界の関心はポスト京都に向けられている。各国政府は、京都議定書が失効する2012年以降、より厳しい削減目標の設定を求められるだけでなく、温暖化がもたらすさまざまな影響から地球を守るために、追加措置の交渉を迫られることになるだろう。
これらの交渉の舞台となるのが、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)の締約国会議だ。本稿執筆時点では、次回会合は2007年12月にバリ(インドネシア)で予定されている。しかし、既に多くの政府や関係者が、独自のコンセンサスづくりを開始している。G8や経済協力開発機構(OECD)が、その例だ。
残念ながら、他の機関は既得権益を守るために、将来の合意をいかに緩やかなものとするかに奔走している。米政府が最近行った一部の東南アジア諸国との会合が、その例だ。 |
|
 |
労働者への影響
労働組合も、これらの会合と無関係ではあり得ない。温暖化が労働者の生活に直接、影響を与えることを国際社会に訴えていく必要があるからだ。最近頻発しているハリケーンや土砂崩れなどの自然災害は、コミュニティーを破壊し、何千人もの命を奪うだけでなく、何百万人もの人々の生活に深刻な影響を与える。しかも、これらの数字は、悪化し続けることが科学的にも予測されているのだ。
労働者とその家族は、温暖化の影響を真っ先に受けると同時に、この問題の解決のカギをも握っている。温暖化をもたらしている産業活動の中心に位置しているからだ。2007年4月、国連安全保障理事会は、気候変動問題を初めて議題に取り上げ、住居や生活を破壊する地球温暖化を、「人間の安全保障」問題と位置づけた。これはまさに、労働組合が10年以上も前から訴えていたことだ。
残念ながら、少エネや技術革新を通じた対策案の多くが、労働者にはマイナスの影響を与えることは否めない。社会や雇用への影響を「グリーンジョブ(環境にやさしい仕事)」や健全な労働環境の創出と結びつける「公正な転換」を通じてバランスを保ち、労働者やコミュニティーが転換コストの負担を不当に強いられることのないようにしなければならない。 |
|
 |
組合の仕事
グローバル・ユニオン(国際産別組織)は、職場を環境に配慮したものにし、労働者個人のエネルギー消費を転換させる制度的・全国的・産業的な枠組みがプラスの変化を生み出すという証拠を示してきた。欧州労働組合連合(ETUC)も欧州各国政府等と協力し、農業、林業、水産、保健、インフラ、エネルギー、交通運輸、製造、建設等の特定分野における変化の道筋を示すための調査報告書を、初めて作成した。
これらの動きは、国際労働機関(ILO)や国連環境計画(UNEP)等が、「グリーンジョブ」や転換プロセスを支持することへとつながった。ゆっくりとだが、労働者や労働組合をも巻き込んだ世界規模のコンセンサスが新たに芽生えつつある。
しかし、各国政府に、より高い目標の設定と転換措置の実行を促す作業は、まだ始まったばかりだ。米国を始めとする先進国に排出目標を受け入れさせ、転換措置に必要な財源を確保させることが成功の鍵といえるだろう。
京都議定書の目標義務から米国等は除外されているが、ブラジル、中国、インド等の新興国に対しては、温室効果ガス削減対策をしっかり実施するように説得していく必要がある。労働組合は他の利害関係者と共に、この問題を自国政府に訴えていかなければならない。
その手段の開発を担っているのが、OECD労働組合諮問委員会(TUAC)の持続可能な開発ユニット(TUSDU)だ。エネルギーや気候変動に関する国ごとのプロファイリングを行い、気候変動に関する労組の暫定委員会を設立して活動の調整に当たったりしている。
国際レベルで気候変動問題に取り組む組合活動家の多くは、バリ会議こそ将来の枠組み合意に労組の問題を反映させる絶好の機会だとみている。
バリ会議に参加するグローバル・ユニオンの代表団は京都議定書後のより高い目標を設定するよう、各国政府の代表団に強力なロビー活動を展開することだろう。グローバル・ユニオンは、過去の会議でも、雇用の移行や、グリーンジョブ、労働者の参加等の問題を訴え、それが京都議定書の現在の削減対象期間に部分的に反映されている。
今日、気候変動との闘いは政治的な色彩が濃くなり、後退の可能性も高まりつつある中、労働者や労働組合に課せられた課題は重く、バリ会議の代表団への参加を呼びかけるITUCの要請も、これまで以上に重要な意味をもっている。
国連気候変動会議(UNFCCC)事務局は2006年以来、企業、NGO、研究機関と共に、ITUCを交渉プロセスの正式な参加者として認めている。バリ会議は、労働組合がこの新しいステータスを使って、政府と共に、長期的に支持することのできる道筋を切り開くことができるかが試される場所となるだろう。 |
|
 |
| ルシアン・ロイヤーはITUC-TUACの職業安全衛生・持続的開発部長。 |
 |
教宣資料として
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動関連調査を担う国際機関だ。世界中の科学的・技術的知見を集約し、評価報告書を発表する。最新の「第4次評価報告書」の作成には、2,500人以上の科学者が参加している。
IPCCは「第4次評価報告書(2007年)」の中で、地球の気温上昇を2度以下に抑制するためには全世界の温室効果ガス排出量を、2050年までに50〜80%削減する必要があるとし、各国の政策立案者には最も低い数字、50%に基づいて政策決定することのないよう警告している。より詳しい情報は、IPCCのホームページ()に掲載されている。
国連気候変動会議(UNFCCC)も、気候変動の影響を緩和させるために、より総合的な目標が必要であることを説明する背景資料や教宣資料を作成している。これらの資料も、UNFCCCのホームページから入手できる。() |
|
 |
| |
|
 |
|