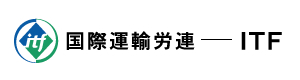|
 |
| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■説得の力 |
 |
| |
説得の力
インド港湾の組織化
新規労働者に対する忍耐強い教育、組織化が、インドの港湾でどのような成果を生みだしたかを、マヘンドラ・シャルマが語る。
インドには、17,516.6キロメートルの海岸線沿いに12の主要港と185の中小港が存在する。そのうち、61港が機能している。
インドの港湾は、1908年のインド港湾法と1963年の主要港管理法の2つの法律で管理されている。グジャラート州、マハラシュトラ州、タミルナドゥ州の沿岸3州には、地方港を開発するための海事局が設置されている。グジャラート州の地方港、ピパブ港とムンドラ(アダニ)港の取扱い貨物量は大きく、マースクとP&O(現在はDPW)がピパブとムンドラで株式をそれぞれ保有している。
1990年代初頭まで、インドの港湾は国の管轄下に置かれ、歴史的に、力の強い戦闘的な労働組合が複数存在していた。1991年に始まった経済自由化の波は港湾にも押し寄せ、政府は協業化についての議論を始めた。しかし、最終的に民営化につながりかねない協業化は労働組合の激しい抵抗を招いた。
改革は世界的な傾向で、世界各地で実施されていた。改革の影響は雇用にも及び、人員削減や労働条件改悪が断行されていった。インドだけが改革から逃れられるとは思えなかった。 |
|
 |
労働者を守るために
無秩序な日雇い化から港湾労働者を守るために、ITFは1993年にハンブルグで開かれた港湾部会で、「世界港湾労働者憲章」(以下、港湾憲章)と「モデル技術協約」を採択した。港湾憲章は、雇用を守るための基本的原則を、ILO第137号条約と第145号勧告に照らし合わせながら設定したものだ。
1994年、ITFデリー事務所は、構造調整プログラムとインドの港湾労働者への影響に関するセミナーをバンガロールで開催し、港湾憲章について話し合った。組合幹部は、改革が避けられないという認識はもっていたものの、近い将来、港湾産業構造が劇的に変化し、中小港湾が貨物の取扱いで重要な役割を果たすだろうことを受け入れられないでいた。一方、経営側は同じ頃、余剰労働力の見直しを始め、港湾経営立て直しのための人員削減を提案して来た。
1995年、ムンバイ港が初めて、労働力を減らすための希望退職制度を導入した。この制度は97年と2000年にも同港で実施され、約7千人の労働者が港湾を去って行った。他港でも同様の制度が実施され、経営側が望んでいた以上の労働者が退職を選んだ。
1996〜1997年には11の主要港で93,876人の常用労働者が雇用されていたのに、2006年3月までには70,250人に減っていた。労働者の総数が減ったわけではなく、日雇いや下請労働者が増えたのだ。 |
|
 |
日雇い労働者
ITFは教育活動を通じて、P&OやDPI、PSA Sicalが運営する新設のグローバル・ネットワーク・ターミナル(GNT)で日雇いや契約労働者などを組織できなければ、組合は将来的に交渉力を失ってしまうと繰り返し警告してきた。しかしながら、組合が新設ターミナルや中小港の組織化に力を入れることはなかった。
ITFは、あきらめずにカルカッタ、コチン、ムンバイ、チェンナイ、ビシャカパトナムで、港湾改革に関するセミナーを実施した。セミナーの目的は港湾産業の急速な変化に備え、新たな分野の組織化を進めることだった。
このセミナーのおかげで、組合は組織化の手法を見直し、生き残りをかけて持てる力を結束する必要性に気付き始めた。JNPTのナバ・シェバ・コンテナ・ターミナルやチェンナイ・コンテナ・ターミナル(CCTL)などでは、地元の労働者たちが経営寄りの労働組合を設立した。
このCCTLの労働組合は、すぐに独立し、争議行動を展開し、団体協約を締結した。しかし、その力を持続させることはできず、山猫ストが頻発したこともあり、幹部全員が解雇され、組合はバラバラになってしまった。もう1つの重要な展開は、2001年2月、チェンナイの外側のエノレに、政府がインド初の公的協業港を設立したことである。 |
|
 |
難題に挑む
近年、組合の姿勢は変わり、民間請負業者等のサービス提供業界で働く労働者を組織するために、規約改正までする組合もでてきた。例えば、ツチコリン港湾一般労組(TPWGSU)は、PSA Sical ターミナルの組織化に取り組んでいる。
また、コチン港従業員組合(CPSA)は、民間部門の労働者のための独立支部を設立し、300人を加入させているほか、マドラス港従業員組合(MPTEU)は、現代自動車ターミナル・バースの労働者を組織し、2006年4月に遡って社会保障手当を勝ち取った。
カンドラの運輸港湾労組(TDWU)は、ムンドラ港のDPWに支部を設立、ムンバイの運輸港湾労組(TDWU)は長い闘争の末にゲートウェー・インド・ターミナル(マースク)の請負会社で働く運輸労働者2,000人以上を組織した。
TDWUが新たに組織した労働者が組合加入を理由に解雇された時、TDWUはITFの支援を受けながら抗議行動を展開し、リアル・ロジスティクスの運転手20人を職場復帰させた。現在、ゲートウェー・インド・ターミナルのもう1つの請負業者であるSCThakur&COの運転士5人の職場復帰を求めて闘争中だ。
このように、インド港湾労組の経験から言えることは、忍耐強く、説得や教育活動を継続すれば、最終的にはGNTなどの民間オペレーターの組織化に道が開かれるということだ。
このような運動は、ムンバイ近郊のダハヌ港での労働組合の新設にもつながった。港湾から遠く離れた内陸コンテナデポ(ドライポート)の組織化の動きも出ている。主要港を組織する全インド港湾労連(AIPDWF)は現在、中小港やターミナルを組織する組合にも加盟の道を開こうと、規約改正を提案している。
インドの港湾労組はゆっくりと、しかし着実に組織化の道を歩み始めている。 |
|
 |
| マヘンドラ・シャルマはITFアジア太平洋地域部次長。 |
 |
| |
|
 |
|