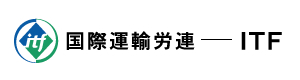|
 |
| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■読者の声 |
 |
| |
アフリカ南部の女性鉄道労働者
■職場には6つのトイレがあった。全て男性用だ。その内2つを女性用に変えようとした。そうすればトイレに行くために1キロも歩かなくて済むからだ。しかし、男性陣は「俺たちはここで20年間も働いているのだから、トイレは俺たちのものだ」と主張した。同僚とは思えない。スト寸前までいった。
■クレーンがあるので、重いものでも運べる。スパナを使う時、油やほこりに接触することもあるが、防具がある。普通の労働環境だ。男性でなければ鉄道員になれないということはない。
■男性のせいで組合内で疎外感を感じることも多い。ある男性から“コムラッド(同志)ママ”と呼ばれたので、「そんな風に呼ばないで。見下された感じがするわ。ただ“コムラッド”とだけ言えばいいじゃない」と言い返した。
■男性には女性が必要だ。女性が何でもやっている。私は転轍手だが、男性にできて女性にできないことは何もない。職場でも、家庭でも、地域社会でもだ。
■機会を与えられているのに、それを活用しない女性もいる。
■2001年、妊娠8ヶ月まで運転していた。周りからの支援は一切なかった。私は管理職だが、管理職のほとんどは男性だ。彼らは女性の管理職を望んでいない。追い出すのに必死だ。
■私の国では、運転士、転轍手、アシスタントは男性だけだ。転轍手やアシスタント運転手になるためには、鉄道員としての経験が必要だ。
■私は転轍手からスタートし、アシスタント、運転士になった。仕事はそれほど大変だとは思わない。熱意の問題だ。女性の運転士がまだ誕生していない国では大変かもしれないが、不可能なことはない。
■募集があっても女性が応募しないこともある。
■転轍は難しい仕事だが、熱意とやる気の問題だ。
■男性組合員は女性を励ましてはくれない。組合が女性を支援すれば、それがスタートとなるだろう。
■私の職場では、妊婦もブーツやズボンなどを着用しなければならない。たとえ着心地が悪くてもだ。今はマタニティードレスが許されるようになった。
■女性側に問題がある時もある。産休明けは軽い業務に就ける権利があるのに、いきなり車庫に戻りたがる人もいる。
■われわれが闘いを通じて勝ち取ってきたもののために命を落とした者もいることを組合員に教えようとしている。われわれが勝ち取った政策を維持・尊重し、活用しなければならない。与えられた産休・育休を全て消化せずに職場復帰したがる人には、文書で理由を説明するように指導している。会社側は、すぐ前例を当てはめようとするからだ。
■技術系の仕事をまかされる、恵まれた立場にいる女性は多くない。技術系の仕事は、ほとんど男性に与えられている。一般的に女性は男性よりも劣っているとみなされているため、チャンスを与えられない。しかし、中には能力を認められ、フォークリフトや新技術を扱う仕事を与えられている女性もいる。
■最近、所有形態が変わり、大規模な人員整理が行われた。新しい経営者は、さらに人員削減、賃金カットを進めている。組合の力は弱まり、組合員や信頼を失っている。組合が何も言わなければ、われわれは声を上げることができない。会社側は、やりたい放題で、職場の雰囲気も威圧的になる。 |
|
 |
| 2007年に開催されたITF女性鉄道労働者セミナーでのコメントから抜粋。 |
 |
| |
|
 |
|