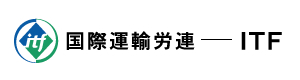| 2008年1〜3月 第30号 |
| ■解説 |
 |
| |
ILO漁業労働条約
2007年6月14日、ILO漁業労働条約(第188号)及び勧告(第199号)が採択された。何年にもわたる困難な交渉を乗り越えての達成である。
今まで漁船員や漁船は既存の法制の多くから除外されてきたが、この条約により、使用者の基本的な義務と、国内措置を定める政府の義務が体系付けられた。
グローバル漁業は、さまざまなかつ幅広い環境と条件下で展開されているので、政府によっては、条約の採択で大きな課題をかかえるところもでてくる。同じく、条約の基本的条項は、投資が進められている企業経営型漁業よりも、開発のあまり進んでいない漁業分野で働く労働者に対して、大きな影響を及ぼすだろう。 |
|
 |
条約が対象とするのは?
条約では、商業漁業に携わる全ての漁船員と漁船が対象となる。つまり、海のみでなく、河川、湖、運河で働く漁船員全てである。全長24メートル以上の船に適用される追加的義務は、もっと小さい船で働く労働者に対して適用することもできる。つまり条約は、全ての漁船員と漁船に適用される一般的条項と、大きな漁船の労働者及び長期間にわたり海上で働く労働者を対象とする追加的条項の二つで構成されている。漁船で働くことが認められる最少年齢は、16才に設定された。 |
|
 |
既存の規制は、どのような影響を受けるのか?
条約に定められる内容より、有利な条件が提示されている法律、判決、習慣、船主と漁船員の協約に対しては、条約は何の影響も及ぼさない。つまり新条約は、世界の中でも規制の乏しい地域において、労働基準を改善していこうとするものであり、ディーセントな労働条件・生活条件を確保する「対等な場」を作り出そうとするものである。 |
|
 |
漁船員とその組合にとって、条約は何をもたらすのか?
条約の下で漁船の船主は、船長を通じて、疲労の予防なども含め船内の安全衛生の確保に責任を負う。今まで労働時間について何の規制も無かったところでは、漁船員に対して、魚がいる限り、安全衛生問題にしばられず漁労活動を続けさせることが許されてきた。しかし、新しい条約では、3日以上海上勤務する場合、強制的に休息時間を確保することが定められた。
24時間のうち、10時間は休息しなくてはならない。7日間のうち、少なくとも77時間は休息しなくてはならない。短期航海の漁船であっても、「十分な」休憩が必要とされているが、これは具体的には定義されていない。全長24メートル以上の船にあっては、安全航行のための最低配乗体制が定められており、必要とされる人数と資格の内容が定められている。配乗体制を証明することについては、特に言及されていないものの、この趣旨の書類をつくる必要性が暗に示されているといえる。
ITF水産委員会議長のジョニー・ハンセンは、「条約は、世界の漁船員の労働条件と生活条件の改善のために待ち望まれていた。まさに出発点となるものである。ITFは、全ての政府に対して、迅速な批准と実施を求めていく」と語っている。 |
|
 |
解釈
条約には、具体的な説明が無いため、文言に幅広い解釈の余地を残している部分が多く見受けられる。その場合、条約本体と同時に採択された勧告を参照することが適切である。
船内で働くものに関しては健康証明が必要になるが、小型の船や3日以内の短期航海の船は、例外とされている。この問題は、交渉の間、長期間の白熱した議論になったものであった。国によっては能力に限界があり、健康診断を行う医療施設が十分に無いためである。こうした問題があったため、ILO漁業条約の中に「漸進的実施」という注目すべき概念を作り出す結果となった(後述の「規則の例外」を参照のこと)。 |
|
 |
実施
条約では、旗国に対し、遵守を強制するシステムを確立するよう求めている。実際には、生活条件と労働条件をチェックするインスペクターを何人か置いて、彼らが検査した船に対して証明書を発行することになる。さらに、入港国も、訴えがあれば調査して、旗国に報告する。漁船員の福利に関心があるものなら誰でも、訴えを起こすことが出来る。「有利な扱いの中止」条項では、未批准の旗国も、批准をした国と同様に、実行を強制する制度を作る義務を負うことが定められた。 |
|
 |
規則の例外
漁業には、先進的な冷凍設備をもつ漁獲加工を一貫して行うような漁船から、沿岸零細漁船まで、さまざまな形態があることから、条約の交渉担当者たちは、既存の基準の大きな差や地理的なばらつきなどの問題と格闘しなければならなかった。基準を出来るだけ高く維持し、既存の体制を損なわないことは重要であるが、基準がまるでないところに、達成可能な最低限の基準を作り上げることも必要であった。
この難題を解決するために、条約は漸進的なアプローチを組み入れることになった。ハードルをあまりにも高く設定することは、多くの漁船員を抱える重要な国々の条約批准を阻害する。そのため、漸進的なアプローチを取り、関係国政府が条約の全ての条項にコミットしつつ、しかも徐々に達成されれば良いとすることで、批准を可能にしたのである。 |
|
 |
より柔軟な対応を
条約の条項の中で、インフラ整備が十分でないことを理由に、漸進的アプローチの対象となりうるものには次が含まれる。
■船内業務に就くための、健康診断書
■クルー・リストの携行義務。なお、リストは陸上にいる指定された者に対しても提供される
■船主が各漁船員と協約を締結する義務
■船内のリスク評価を実行する義務
■職務に関連した疾病、怪我、死亡の場合、保護を提供する締約国の義務
漁業条約批准国には、ここに挙げた条項の実施に関して柔軟性が認められているとはいえ、適用免除が認められない場合もある。例えば:
■全長24メートル以上の船
■海上に7日以上滞在する船
■旗国の沿岸から200マイル以上離れた水域で操業する船、である。
それぞれ異なる困難な問題に対応するために、条約には、複雑な例外措置が組み合わさって含まれている。要するに、使用者の代表と労働者の間で、まず例外措置について話し合うことが必要であり、そのうえで、概ね、これら例外措置を、沿岸で操業する小型船か、短い航海のみ行う船に限定して適用することになる。 |
|
 |
条約はいつ発効するのか?
ILOが、署名の通知を締約国10カ国から受け取った時点で発効するが、その際、沿岸国が少なくとも8カ国含まれていなければならない。これは発効要件としては、いささかゆるい基準である。例えば、2006年ILO海事労働条約の場合は、30カ国の批准が必要であり、しかも総トン数で世界の船腹の33%カバーされている必要がある。
これから見ると、漁業条約は、発効のタイミングという面では、海事条約の上を行っていることになる。どんな速度でことが運ぶか、見守りたい。 |
|
 |
| ITF船員・水産・内陸水運部会上級アシスタントのケイテー・ヒギンボトムによる解説である。 |
 |
漁業労働条約に関する詳細は、
まで。 |
 |
新たな権利
賃金と労働条件
ILO漁業労働条約では、船内にクルー・リストを備え、全ての漁船員が労働協約を携行していなければならないとしている。これらは、条約の付属書IIに詳細が定められている。労働協約には、合意された賃金(漁獲配分の詳細を含む)、職務中の疾病、怪我、死亡の場合の保護措置、社会保障の範囲、帰国の保障が明記されていなければならない。漁船員には月毎もしくは何らかの定期的な形で、賃金が支払われなければならない。
労働協約に関して重要なのは、漁船員が安定した収入を得る権利を確立したことである。労働者と使用者間の労働協約が詳細に記録されるので、争いになっても、文章化された証拠が当事者全ての手に入る。たとえば、入港国担当官も調査が可能になる。お金についていえば、漁船員は乗り組むために必要な料金を払う必要はないとされている一方、国には、漁船員をリクルートする会社を適切に管理する義務が課せられる。
食事、まともな宿泊設備、個人が使用できる防護器具の提供は、船主の責任である。条約の条項に加え、全体を網羅して付属書(アネックスII)が作られ、新規建造船や大幅な改造が加えられた漁船の宿泊設備の要件が定められた。ここは特に交渉で意見が対立した部分であり、地域で実現可能な最善の基準をつくるためには、労働組合からの働きかけの余地が残されている。 |
|
 |
| |