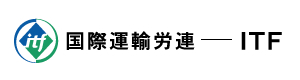|
 |
| 2005年4〜6月 第19号 |
| ■港湾混雑 |
 |
| |
港湾混雑
港湾労組は増え続けるコンテナ貨物への対応策として増員とオペレーション・システムの改善を要求している。
中国やインドといった低コスト国からのアメリカやヨーロッパへの繊維製品の輸入を制限してきた、WTOの多国間繊維取決め(MFA)の段階的撤廃が2005年1月に完了する。これに伴い、1959年以来初めて先進国の繊維市場が無制限に開放される。インドや中国は今、スリランカやバングラデシュなどの小規模輸出国だけでなく、欧米国内の生産業者をものみこむ勢いで、輸出攻勢をかけようとしている。
この新たに自由化された繊維市場で、苦戦を強いられる既存業者も出てくるだろう。同時に、このような国際貿易形態の変化は船社や港湾業務にも大きな影響を及ぼすだろう。既にグローバル化の影響で貨物取扱量が大幅に増加している輸入国の港湾は飽和状態に達することが予想される。WTOの予測によると、米国の繊維製品輸入における中国のシェアは今後3年間で45%に増え(現在は16%)、第2位のインドは2002年の5%から18%に増える。一方、中国は既に輸出全体の18%を占める繊維製品の生産を今後さらに増やしていくことが見込まれる。コンテナ船の船主にとっては朗報だが、資金不足の港湾にとっては頭の痛い問題だ。
|
|
 |
需要増への対応
中国は増える外国需要に対応すべく、国内輸送モードの整備に追われている。港湾、航空、高速道路に大規模な投資を行ったほか、全国のコンテナ倉庫を鉄道で結ぶ計画も発表した。大手船社のCoscoは、欧州港湾への投資を自社の重要な成長戦略の一部とみなしている。Coscoの魏家福総裁は2004年12月に業界紙ロイズリストに対して、中国貨物取扱量欧州一のハンブルグ港にコンテナターミナルを建設するために5億ユーロの投資を検討していると語っている。これは11月に同社が実施した、アントワープ港(ベルギー)のコンテナターミナルへの大型投資に続くものだ。このターミナルはCOSCO、P&Oポート、P&Oネドロイド、ドゥイスポートの合弁で、COSCOは株式の25%を所有している
港湾オペレーターは時として特定の船社専用のターミナルの建設に否定的だが、キャパシティー拡大の緊急性を認識しているのはハンブルク港だけではない。たとえ中国製繊維製品の需要急増を考慮に入れなかったとしても、製造や貿易のグローバル化が未曾有のスピードで進む中で、輸入国サイドはロジスティクス上の種々の対応を迫られているからだ。米国務省は昨年末にOECD海運作業部会に提出したペーパーの中で次のように述べている。「最近の国際貿易パターンの変化に伴う輸入増は、長期的課題を緊急課題に変えた。しかも、この変化は一時的なものではなく、米国の輸入需要は恒久的に上方シフトした模様だ。製造業はアジア、特に中国に集中している。2004年1月〜7月の対アジア物品貿易の伸びは19.5%に達しているが、対中国に至っては87.4%と爆発的な伸びを示しており、昨年同期に比べて30%増えている」
さらにこのペーパーは、船社が追加的サービスや大型船舶の投入で需要急増を乗り切ってきたのに対して、アジア貨物の大部分を取り扱う西海岸の港湾は労働力不足のためにうまく対応できなかったと指摘している。「西海岸の港湾は俗に言う“カジュアル(非正規)”労働者3千人を追加雇用する予定だが、彼らが重機やクレーンなどを操作できるようになるまでには相当の訓練と現場での経験が必要だ」
|
|
 |
労働力不足の危機
2004年11月、米国西海岸の港湾労働者を組織する国際港湾倉庫労働組合(ILWU)とITFは共同声明を出し、主要港における労働者の雇用・訓練規模を拡大し、非効率的な港湾設備を改善することで、世界的な海運需要の増大に対応するよう、ターミナル・オペレータなどの港湾運送事業者に要求した。
このような組合の要求は記録的な船混みに業を煮やした業界幹部数名からも支持されている。ITFとILWUが共同声明を出す前に、大手船社2社が、国際貨物の流れをスムーズにするのに必要な熟練労働力に投資するよう、ターミナル・オペレータに圧力をかけると明言した。日本郵船とP&Oネドロイドはロイズリスト上で、貨物の混雑を緩和できない言い訳ばかりしているとして、ターミナル・オペレータを非難している。「海運需要が予想を上回る伸びを示す中で、欧米港湾の労働力不足が海運業界全体にとって深刻な問題となっている」と日本郵船の小澤幸夫専務は指摘する。一方、米国西海岸の港湾労働者は、安価な海外製品の国内需要に応えるのに十分な労働者を雇用・訓練するよう何ヵ月も前から要求していた。
「われわれは2004年2月にロサンゼルス港とロングビーチ港で数千人規模の雇用拡大を提案した。8月にこれが実現し、ついに需要に見合うだけの労働力が確保された。新たに雇用された労働者は現在、訓練を受けている。短期的思考で貨物の混雑が緩和するわけではない。トラックのアイドリングや設備の老朽化による環境汚染が減少するわけでもない。ILWUはサプライチェーンの中で貨物をスムーズに移動させる革新的な方法を4年も前から提案してきた」とILWUのジェームズ・スピノザ委員長は言う。
「ターミナル・オペレータは、よく訓練された港湾労働者が海運業界や港湾荷役の安全・安定に不可欠だという国際労働界の主張に耳を傾けてこなかったが、他の業界関係者は今、熟練労働者が業界の利益に貢献することに気付き始めている。これをきっかけに業界の姿勢が前向きに変化することを望む。ILWUとITFは設備投資や人材の訓練・育成に積極的な港湾が業界のモデルとなるよう、引き続き活動を進めていく」とITFのフランク・レイ港湾部長は語った。
|
|
 |
米国西海岸の港湾混雑要因
スティーブ・スタローン著
米国西海岸港湾の最近の混雑はインフラやプランニング上の数々の問題が重なり合った結果で、今や海運業界全体がその影響を被っている。われわれの警告で根本要因への対応が行われるかどうかはこれからが見ものだ。
ことの始まりは鉄道会社が人件費を減らすために早期退職制度を提案したところ、予想を上回る数の従業員がこれに応じて退職したことだ。このため、機関車や車両に加えて、熟練労働力も不足し、ピーク時の膨大な貨物量に対応できなくなった。そのため、鉄道会社はロサンジェルス/ロングビーチ地区のターミナルから受け入れるコンテナの量を制限し始めた。
ドミノ現象
その結果、港にコンテナが滞留し始め、ターミナル・オペレータはコンテナを車両積み(シャーシ・システム)から地上積みへと変更せざるを得なくなった。このため、トラックや列車にコンテナを積み替える際に必要な重機運転手の数が6倍に膨れ上がった。運転手は急激に不足し、全船舶に対応できるだけのギャング(作業班)も確保されず、港内の混雑は悪化していった。さらに悪いことに、コンテナの滞留や重機不足で荷役効率も下がっていった。また、ターミナル・オペレータはトラックゲートを日中しか開放しないが、これはつまり、鉄道コンテナ以外のコンテナの出口が非常に狭いことを意味する。
一方、使用者側はこれほど多くの貨物がやって来るとは予想していなかったと主張するが、業界アナリストが何年も前から年間二桁台の貨物の伸びを予測していたことを考えれば、この主張が言い訳に過ぎないことが分かる。ここ数年間、使用者側は組合の提案を「自分たちの仕事と雇用を増やそうとしているだけ」と聞き流してきた。しかし、状況が変わり、今や組合の提案のいくつかを受け入れざるを得なくなっている。
組合の警告
ILWU南カリフォルニア支部が2004年2月に雇用規模の大幅拡大を要求していたにもかかわらず、使用者側が新規の雇用計画に合意したのは、港湾混雑の問題が国際的に不名誉な段階にまで発展した8月になってからのことだった。今や2005年のピーク期までにさらに雇用を増やすことが検討されている。
また、ILWUはトラックゲートを24時間とまでは言わないまでも、少なくとも夜間シフト中は開放するよう、何年も前から要求していた。今、使用者側はこのような体制を今春までに実現できないか検討中だ。
さらに、ILWUはゲート付近にトラックの待機場所を設置し、トラックをドックに入れさせないことで混雑を緩和し、貨物の移動を円滑化することも提案している。
この提案はまだ受け入れられていないが、2005年のピーク期を前に使用者側に選択の余地はないだろう。道路建設や鉄道拡張、コンテナヤード拡大などの大規模インフラプロジェクトはこれから数ヵ月間で完成するものではないからだ。 |
 |
|
 |
| スティーブ・スタローンはILWUのコミュニケーション部長。ILWU機関誌「ディスパッチャー」の編集長でもある。カリフォルニア在住。 |
 |
| |
|
 |
|