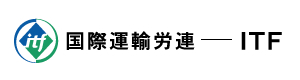|
 |
| 2005年4〜6月 第19号 |
| ■コメント |
 |
| |
福祉国家の再来?
ITFのケース・マーギス前港湾部長が明るい兆しを指摘する
資本主義のドグマに支配された現代という時代は1973年9月11日のサンチアゴ(チリ)で始まった。この日、一人の将軍が民主的に選出された政府を転覆させ、反対派を何千人も殺害した。当時、頑強な社会主義者だったアレンデ大統領は貧困と闘い、福祉国家の樹立を目指していたが、ピノチェト将軍とその支持者らは国家の行き過ぎた経済介入の「排除」を主張した。
ピノチェト将軍が影響を受けたのがシカゴ在住のアメリカ人教授、ミルトン・フリードマンだった。フリードマンは2つのことを信奉していた。金と自由だ。フリードマンは、当時、多くの国で深刻な問題となっていたインフレは政府が経済に大量の資金を投入し過ぎた結果であると指摘し、個人や企業は経済活動を実施するにあたりできるだけ多くの自由を与えられるべきだと説いた。
フリードマンは最も辛口の経済学者として知られるようになり、小さな政府、低税率、自由市場、民営化を主張、当時主流だったケインズなどの英国リベラル派の理論(人間の顔をもつ、よりソフトな資本主義論)をも攻撃の対象とした。人間的側面はあまり考慮せず、市場の機能と民営化を中心とする基本的形態の資本主義、つまり市場原理主義を推奨した。
1976年にノーベル経済学賞を受賞すると、ピノチェト将軍などの軍部だけでなく、英国のサッチャー元首相(1979〜90年)や米国のレーガン元大統領(1981〜89年)なども彼の理論の影響を受けるようになった。
|
|
 |
変化の兆し
その結果、これらの国々で経済改革が開始されたが、全ての人に富を与えるという当初の目的は物の見事に失敗した。この種の経済改革は今なお多くの国で実施されているが、最近になって、強い国家の新たな役割を示唆する評論家が現れ始めた。市場自由主義者として知られる者でさえも、自由な国際金融市場がもたらす危険性を警告している。例えば、英フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、マーチン・ウルフは自らのコラムや著書「Why Globalisation Works(なぜグローバル化が機能するのか)」の中で悪い統治(バッドガバナンス)が壊滅的な影響をもたらす可能性を訴えている。
ウルフは良い市場には良い政府が必要であり、良い政府には良い市場が必要だと説き、もう一人の著名な米経済学者、ジョセフ・スティグリッツの言葉を引用し、中南米と東アジアの金融危機を引き起こしたとして商業銀行を非難している。
ウルフは金融と貿易を区別し、貿易の自由化・グローバル化(ウルフはこれを「経済活動の国際統合」と表現している)は支持するが、現在の形態の金融の自由化には反対の立場をとっている。
思考の変化の兆しとしてさらに驚くべきものはフランシス・フクヤマ教授(ベストセラー「歴史の終わり(The End of History)」や「最後の人間(Last Man)」の著者。影響力のある右派系シンクタンク「アメリカ新世紀プロジェクト(PNAC)」のメンバーでもある)に見られる。 |
|
 |
過ちに気付いて
新書「State Building(国づくり)」の中で、いわゆる構造調整プログラムの多くが途上国で失敗した理由を次のように説明している。
「問題は、国家の役割を削減すべき分野もあれば、強化すべき分野もあるという点だ。自由化を推奨する経済学者たちは、この点を理論上は完璧に理解していたが、当時、国家活動の削減にあまりにも焦点があてられていたため、彼らの理論は国家の役割の全面的削減という風に誤解されたり、あるいは意図的に解釈されたりした。国づくりは少なくとも国家の役割の削減と同じくらい重要であるにもかかわらず、ほとんど注目されなかった。その結果、経済自由化の改革は多くの国で本来の目的を果たすことができず、しっかりした制度的枠組みが存在しない国の中には、自由化前よりも貧しくなったものもあった。」
だが、彼の著書「State Building」の中で最も印象的なのは、市場原理主義や民営化の父と言われるミルトン・フリードマンの引用句だ。
−彼(フリードマン)は社会主義からの移行国に対して10年前なら3つの言葉を送っただろうと言う。つまり「民営化、民営化、民営化」だ。しかし彼は「自分は間違っていた」「法の支配とは恐らく民営化よりもずっと基本的なものなのだろう」と続けた−
もちろん、ウルフもフクヤマもフリードマンも労働者の保護者、あるいは社会の守護神という過去の輝かしい形態の国家再来を主張しているわけではない。
しかし、こういった兆の中に、振り子の針が元に戻り、福祉国家再来の予告を感じるのは楽観的すぎるだろうか?国家の形態をどのようなものにするかは今後の議論と行動次第だ。アレンデ大統領は二度と戻ってはこないが、われわれは労働者として、また組合活動家として、福祉国家再生の機会を逸してはなるまい。連帯のグローバル化の究極的な目的として、21世紀にふさわしい、持続可能な国づくりを進めていきたい。
|
|
 |
| ケース・マーギスは前ITF港湾部長。現在は労働組合に関する執筆やコンサルタントを務めている。 |
 |
| |
|
 |
|