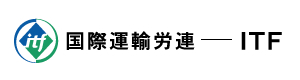| 2005年4〜6月 第19号 |
| ■都市交通の暴力撃退 |
 |
| |
攻撃撃退
ITFの調査からもその必要性が明らかになったILOの新行動規範は、組合員に対する暴力を撲滅しようという都市交通労組の取り組みに役立つだろう。
今年、国際労働機関(ILO)は、職場の暴力に関する新しい行動規範を各国の省庁、使用者、労働組織の間に広める活動を完了する予定だ。
この10年間、都市交通部門では、一般的に交通運輸労働者や乗客に対する暴力の報告件数が増えている。報告システムが改善され、またマスコミの関心も高まったことが、報告件数増加の一因であろうが、問題の核心はあくまでも社会経済的要因にある。
初期に出されたILOの報告書は、交通運輸が繰り返し暴力行為の標的にされてきたのは、一定の弱点があるからだと指摘した。その弱点の中には、時代に関係なく常に存在してきたもの、交通運輸産業に特有のものもあれば、現在の業界や景気の動向によって悪化したものもある。
鉄道の駅やバスのターミナル、旅客を乗せる車両そのものが、「状況的に犯罪を誘発する機会」をつくり出してしまう。特に周囲が静まった夜間は、一人になった夜勤中の運転手や車掌を容易に襲うことができる。タクシー運転手や車掌が運賃を払おうとしない乗客に払わせようと譲らなければ、もめ事が起こりやすくなる。
多くの国で、バス、タクシー、トラックの運転手が検問や国境地帯で、軍人や警察、税関職員から嫌がらせ受けたり、略奪されたりしたと言っている。また、国によってはインフォーマルで無規制の旅客輸送サービスが増えており、運転手が一人で運転することも多いため、嫌がらせを受けやすくなる。また、産業自体がILOの指摘する「熾烈な競争と無規律状態」に陥りやすくなっている。
正規の公共交通サービスもまた、コスト面や競争面で圧力にさらされている。規制緩和と民営化は、多くのサービスの過少投資を招き、それが交通渋滞やサービスの遅れ、最終的には乗客の不満につながっていく。同時に、保安員や検査官、発券係などの従業員数が減少すれば、暴力事件を阻止したり、目撃したり、それに対応する従業員の数も減少することになる。
ILOの行動規範が明らかにしているように、政策、防御手段、対応プログラムを作成する責任は政労使にある。対処すべき問題の深刻さと特徴を理解してもらうためには、まずは情報収集から始めなければならない。
ILO行動規範の採択から4ヵ月後の2004年2月、ITFは都市交通産業の加盟組合に2つのアンケートを送付した。アンケートの目的は、暴力に関する運転手の経験と、暴力に対する組合の方針について理解することだった。
回答はかなり少なかったが、13組合が個人的な暴力体験を、23組合が組合の方針について報告してくれた。世界の各地域から回答を得たが、2つのアンケート全体で見ると、欧州からの回答が全体の3分の2を占めた。
|
|
 |
調査結果―暴力の体験
第一のアンケートに回答した400人以上の運転手のうち、大部分がバスや列車の運転手として経験が10年〜30年あった。タクシー運転手40名、数名の地下鉄、その他トラム、軽電車(ライトトレイン)、長距離バス、ミニバスの運転手などが回答してくれた。女性の回答者は全体の4分の1以下で、女性に特有と思われる問題についての報告はなかった。
全回答者の6割が身体的、あるいは言葉による暴力を受けた、あるいは威嚇されたことがあると回答した。一部回答者は数回にわたる経験を報告し、攻撃を受けた運転手が意識を失ったという報告が7件あった。
暴力を受けたことのある運転手のうち、67人は身体的な暴力を受け、54人が負傷、20名が入院する必要があったと回答した。暴力を受けた後、カウンセリング、治療、補償などの面で支援が得られたと答えた回答者はたった3割だった。安全モニターや警報機の設置、無線やビデオシステムの導入、施錠、警報ボタンの設置などの方法で、使用者あるいは自らが暴力から身を守っているという回答者が4分の1を占めた。
車両に警報システムや追跡システムが備わっているという回答は3分の1以下だった。使用者が暴力を防御し、暴力に対処するためのガイドラインを設けていると答えたのは、わずか22パーセントだった。しかし、一方で、労働者は職場の安全を向上させるためにあらゆる手段を編み出している。(詳細は囲み記事『運転手の要望』を参照)
例えば、夜勤時に警察から協力を得る、加害者への懲罰を厳格化するなどの面で、当局との緊密な協力関係構築を提案する声も、労働条件改善のための提案と並んで多かった。警報機、追跡システム、ビデオ、施錠システムの導入などの技術面での提案もあった。
|
|
 |
労組の方針
第二のアンケートに回答した労組の大部分は、路面や鉄道旅客サービスに従事する労働者を代表する組合だった。これらの組合は、事務部門・非現業部門の労働者も組織しているが、回答した23組合のうち、組合員が職場で受けた暴力を記録に残していると答えたのは9組合だけだった。7労組が組合員を職場の暴力から保護するための特別条項を団体協約に盛り込んでいると答えた。そのような条項には、監視ビデオや暴行を受けた際の連絡用電話の設置なども含まれている。
回答した組合のうち4分の3が、仕事関連の事故については組合員が報告と記録を行っていると答えた。場合によっては職場に安全職員が派遣されることもある。企業が保険手続きのため、書類を記入しなければならない国もある。
半分の組合が、暴力の予防策や万一発生した場合の対処の仕方などを定めたガイドラインを使用者が設置していると答えた。その中には、諍いが発生した場合の対処法、防御法、救済の求め方、ビデオによる監視、無線による検査に関する訓練プログラムの規定も含まれている。
最近職場の暴力を防ぎ、暴力に対処するための提案づくりや活動に参加したと答えた組合が20もあったことは心強い。具体的には使用者、地方当局や自治体との合同作業部会への参加、記者会見、ストライキ、交通運輸サービスの利用者に向けた啓蒙キャンペーン、警備員の配置、警察の協力、運転手の法的な支援、加害者への懲罰の厳格化を求める取り組みなどが行われている。
調査結果について、ITFの浦田誠・内陸運輸部長は、「回答した組合の数は多くはなかったが、これらの調査から、都市交通の労働者が何を経験し、また組合が弱い立場にある労働者に対する暴力を撤廃するために行っている様々な取り組みについて有益な情報を得ることができた。ILOの新行動規範がより広まることで、組合員を守るために不可欠な方針や規定を組合が確保する際の良い手本になってくれればと願う」と述べた。
|
|
 |
ILOの行動規範 中心となる問題
政策には少なくとも下記の事項を含めさせる。 |
| ■ |
職場における暴力の定義 |
| ■ |
職場の暴力を許容しないという声明 |
| ■ |
暴力の無い職場環境をつくることを目指す、あらゆる行動を徹底的に支持する。 |
| ■ |
報復、濫用、安易な申し立てなどとは無縁の公正な苦情システム |
| ■ |
労働者と一般市民向けの情報と教育 |
| ■ |
職場の暴力を防御、管理、是正、排除するための方策 |
| ■ |
暴力事件の仲裁と管理に関する方策 |
| ■ |
徹底して政策を広める態度 |
| ■ |
秘匿性 |
|
職場の安全に関する問題
サービス業の職場における暴力発生のリスクを最小限に抑えるため、下記を考慮すべき。 |
| ■ |
特に危険な地域やリスクレベルを特定する |
| ■ |
駐車場や輸送施設などの職場へのアクセス提供 |
| ■ |
保安サービスの存在 |
| ■ |
職場の見通しを悪くする障害物の排除 |
| ■ |
立ち入り禁止区域の指定 |
| ■ |
労働者やその代表者と協議し、危険地域に保安システムを設置 |
| ■ |
仕事に必要な場合を除く、武器の持ち込み禁止 |
| ■ |
職場での飲酒、麻薬の禁止 |
| ■ |
労働者やビジターの適切なアクセス制限(ID、受付、ゲートなど) |
| ■ |
必要に応じた労働者のためのIDドキュメント |
| ■ |
必要に応じたビジターのためのIDドキュメント |
| ■ |
企業全体の保安に関する企業内での協力体制 |
|
|
 |
ILOの「サービス産業の職場における暴力に関する行動規範と暴力への対応策」
() より抜粋 |
 |
| 運転手の要望 |
| ■ |
労働時間の短縮 |
| ■ |
労働者を暴力から守る防御手段を団体協約に盛り込む |
| ■ |
車掌の配置などによる二人体制 |
| ■ |
乗客管理のため、保安員を増員する |
| ■ |
遠隔地で乗客の待ち時間を短縮する |
| ■ |
予防と対処のための訓練機構の設立 |
| ■ |
予防的な防御手段、評価方法の導入 |
| ■ |
攻撃の防御策と事件発生後の対応策に関する明確な指示 |
| ■ |
効果的カウンセリングと攻撃を受けた後の被害者への支援 |
|
|
 |
| |