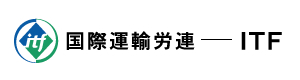|
 |
| 2009年10〜12月 第37号 |
| ■コチン港の闘い |
 |
| |
経済危機と闘う港湾労働者
ITF港湾部会は経済危機の影響を最小限に食い止めるために活動しているとフランク・レイは言う。
世界経済危機の港湾労働者への影響は深刻だ。だからこそ、ITFとその加盟組織は、主要企業に関与し、労働者への影響を最小限に食い止める活動を行っている。
港湾労組は世界各地にターミナルを展開するグローバル・ネットワーク・ターミナル(GNT)への対応が重要であることを認識している。
GNTはコンテナ輸送に関して、既に多大な影響力を持っているが、今後、既存のターミナルを買収したり、未開発地に新規ターミナルを建設したりすることで、さらに影響力を増していくことが予想される。
ドゥルーリー・シッピング・コンサルタントによると、4大大手のハッチソン・ポート・ホールディング、APMターミナル、PSAインターナショナル、ドバイ・ポート・ワールドは、2007年、4社間で2億2,430TEUを動かしている。これは、世界のコンテナ取扱量の45.1%に相当する。
民営化されたターミナルのコンセッションを通じて新たな投資機会を追求したり、さらなる競争力・収益力確保のためのビジネス戦略を追及するGNTは、その規模と影響力の大きさゆえに、世界の港湾労働者の雇用にも大きな影響を及ぼし得る。
組合がGNTと関与する機会は存在する。社会対話の慣行や、力のある労働組合が存在する場合は、既存のルールを尊重し、労働組合と関わり合いを持つことを彼らは表明している。
しかし、これらを彼らに義務づける法律が存在しない場合や、組合の地位が弱く、社会対話の相手として尊重されにくい場合は、建設的な対話を持つことが難しい。
ITFがGNTとの間に強固な信頼関係を築き、お互いにプラスとなるパートナーシップを構築することができれば、これをローカルレベルで、労使の接触に役立たせることができるだろう。ITFは加盟組織の国内活動に介入しようとは思っていない。加盟組織の建設的な労使関係の構築を支援しようとしているのだ。
もう一つの重要な点は、港湾がサプライチェーンの中に組み込まれているということだ。あらゆる交通運輸部門の労働組合を組織するITFは、港湾以外の産業、例えば、道路輸送、鉄道、倉庫産業の組合との共闘を手助けすることができる。
GNTとのこれまでの協議内容は次の通り。
■労働組合権の尊重
■安全衛生慣行の促進と安全な職場の確保
■良好な労使関係の構築
■景気後退の影響の共同管理
これらの協議が、港湾労働者の雇用・労働条件確保の上で、具体的な成果をもたらすことを期待している。 |
|
 |
| フランク・レイはITF港湾部長 |
 |
コチンのコンテナターミナル
労働者の権利を守れ
コチン港従業員組合(CPSA)のPMモハメド・ハニーフが、雇用・労働条件確保のために、4大大手の一つ、ドバイ・ポート・ワールドといかに交渉したかを語る。
インド政府がラジブ・ガンジー・コンテナ・ターミナル(RGCT)の運営をドバイ・ポート・ワールドの子会社、インド・ゲートウェイ・ターミナル(IGTPL)にBOT方式で移管した際、RGCTの労働者の不安は高まった。
コチン・ポート・トラスト(港湾公社)が管理するインフラおよび職員がIGTPLに移管される一方、IGTPLは、既存のターミナルのコンテナ取扱量が40万TEUを超えた時点、あるいは3年以内に、インド初のトランスシップメント(積替え)用国際コンテナターミナルを新たに建設することとなっていた。(新ターミナルは2009年11月に完成予定。)
RGCTの労働者と組合は、民営化で雇用が奪われるのではないかと懸念していた。
組織化と連帯
当時、コチン・ポート・トラストには、8つの組合が存在していた。私は全組合をまとめ、状況を分析し、他労組の連帯支援を受けながら、合法的に行動を起こすことを決めた。
主な使用者はコチン・ポート・トラスト(CPT)だったため、まずはIGTPL、CPT、8労組との三者協議を要求した。
その後、地方労働委員会にスト通告をし、実行に移すと、地方労働委員会の介入によって交渉が始まった。何度か交渉を重ねた後、2005年3月に合意に達した。
その結果、RGCTの港湾労働者は全員、IGTPLに継承されることとなり、賃金、昇給、労働条件は、CPTの他の労働者と同レベルで維持されることになった。
また、バラルパダムの新ターミナルに移った後も、需要や労働者の適正に応じて、雇用が保障されることになった。RGCTからIGTPLに継承される労働者は、もはやCPTの職員ではなくなり、CPTは年金等の使用者責任から逃れることになる。ラッシングを行っている民間港運会社の従業員の雇用も、この合意を通じて守られることになった。
労使関係の向上
2005年4月に移管が実施されたところ、合意事項の実際の適用に関して様々な問題が発生したが、当時、わが組合は、港湾当局の協力を得ながら問題にうまく対処することができた。IGTPLが合意に違反しようとした時も、わが組合が適切に介入し、問題を解決することができた。現在、IGTPLとは良好な労使関係を維持している。
合意内容は団体協約というより、国内の労働法に基づいた強制的な解決措置であり、CPTに雇用されていた常用港湾労働者352人およびIGTPLへの移管当時の民間契約労働者に適用される。
さまざまな行動を通じて、港湾当局およびIGTPL経営陣に圧力をかけた結果、労働者の権利を守る合意を勝ち取ることができた。コチン港の港湾労働者の連帯も強化された。また、他の問題(国レベルの奨励給およびボーナス制度等)の解決にも道が開かれた。
今回の勝利は、労組間の連帯の結果であり、完全な作業停止に至ることなく問題に効果的に取り組めたことの成果だ。 |
|
 |
我々の目的
ITF港湾部会とその加盟組織は、グローバル・ネットワーク・ターミナル会社に関する活動に取り組んでいる。その目的は…
■地域・ローカルレベルの社会対話に活かすための世界レベルの社会対話
■必要に応じ、最低基準を規定する国際枠組み協定(IFA)の締結を目指す世界レベルの対話
■労働組合権の認知およびターミナルにおける組合認知
■各地の団体交渉および団体協約締結支援
■良好な安全衛生基準の確保
■労組間ネットワークとコミュニケーション
■各組合の運動への連帯と紛争解決支援
■景気後退の労働者への影響の最小化と有効な技術の維持 |
|
 |
| |
|
 |
|