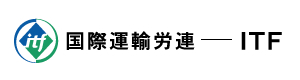|
 |
| No.26/2012 |
| ■水産 |
 |
| |
捕獲から小売りまで:組合の影響力拡大が必須
2011年1月、ITFと国際食品労連(IUF)の合意に基づき、水産業の組織化のためのグローバル・キャンペーンが立ち上がった。労働組合の団体交渉に基づく協約の保護を、より多くの漁業労働者に広げることを目的とするこのキャンペーンの背景には、どのような考えがあるのか、キャンペーンの主導者、リズ・ブラックショーが解説する。
グローバル化と魚の消費量の増加は、水産業の構造に大きく影響してきた。現在では、殆どの企業が総合型の商業ベースの運営を展開している。つまり、多くの企業が魚の捕獲、加工、小売りの全てに携わっている。
そのため、水産業のサプライチェーンを通じて、関係する組合を組織するITFと国際食品労連(IUF)が協力することは極めて重要だ。
総合型の商業水産業界で働く労働者のわずか1%しか組織化されておらず、むろん団体協約も持たないという事実から、組織化の必要性は、明白だ。
最近、いくつかのILO条約が第188号条約に統合されたが、ILO曰く、この条約は「漁船員が船員と同レベルで保護されること」を担保することを目指している。遠洋漁業に従事する漁船員は、同条約の恩恵を受けてしかるべきだ。
ILO第188号条約は2007年に採択されたが、2011年末の時点で、わずか2カ国しか批准していない。
併せて注目しなければならないのは、国際海事機関(IMO)が報告するように、水産業で労災死亡事故件数が年間2万4千件にも上る事実だ。水産業特有の労働災害も一部にはあるが、国内外で安全基準を守らせる手段がないことも、痛ましい死亡事故の主な原因となっている。
水産加工業界の労働条件は、理論的には各国の雇用・安全基準の範疇だが、決められた労働条件を守らせる術は殆どないのが現実だ。加工工場の多くが途上国にあるため、労働者の多くは立場が弱く、不安感から自らの権利のために闘うこともできない。
欧州や中南米では、運動の末、労働者が権利や組合の承認を勝ち取った喜ばしい例が見られるが、世界中で消費されている魚の85%はアジア太平洋地域で養殖・加工されている。
最近、漁業労働者の働く現場を訪れた結果、下記のような驚くべき労働実態が明るみに出た:
| ● |
1,300人もの労働者が、手袋も全くつけずに魚の皮剥ぎ、内臓除去、骨抜きなどの作業に従事していた。 |
| ● |
定期的に賃金や手当てを貰えず、携帯メールでその都度呼び出されて働いている労働者が400人もいる。 |
| ● |
労働者は防護服もつけず、健康への影響についての配慮もなされないまま、マイナス15度からプラス30度まで、非常に温度差のある作業場を行き来して魚を運んでいる。 |
| ● |
労働者の組合加入の動きを阻止するため、解雇、反労組組織の結成、労働者を脅迫して組合を脱退させるなどの行為を含む、非公式な全国レベルの協定が結ばれている。 |
このITF・IUFプログラムには、社会的・環境的側面という、もう一つ非常に重要な要素がある。現在、食物源としての魚の持続可能性について、グローバルレベルで多くの議論がなされている。したがって、労働組合は他の組織とも協力し、他団体のキャンペーンに適正な労働基準の確保が必ず盛り込まれるようにしなければならない。 |
|
 |
主な目的
ITF・IUFプログラムは、以下の目的を持つ:
| ● |
産業化された漁業や水産加工部門における多国籍企業の組合敵対行為や組合回避行為を無力化する。 |
| ● |
他の圧力団体などと協力し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業と闘うよう各国の政府や企業に圧力をかける。 |
| ● |
ILO第188号条約の批准を急ぐ。 |
|
|
 |
| |
|
 |
|